
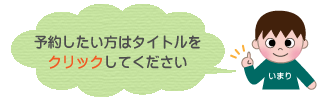
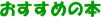
| 『駄菓子屋の儲けは0円なのになぜ潰れないのか?』 | |
| 坂口 孝則/著 SBクリエイティブ 商店街にむか~しからある靴屋、ほとんど見かけなくなったちんどん屋…。「やっていけているのか?」と正直思ってしまう職業の数々。経営コンサルタントがその疑問にお答えします。 個人経営が大手チェーン店に勝るのは、機動力と専門性であると語る著者。実際の事例を数多く挙げながら、多種多様なビジネスモデルを紹介していきます。今の時代だからこそ求められる経営のヒントを探ってみましょう。 (S.S)
|
|
| 『カトマンズに飛ばされて』 | |
|
古舘 佑太郎/著 幻冬舎
(S.T)
|
|
| 『芭蕉はがまんできない おくのほそ道随行記』 | |
| 関口 尚/著 集英社 松尾芭蕉の『おくのほそ道』を従者、曾良の視点から描いた青春小説です。旅を出発した当時の芭蕉と曾良は40代。壮年期二人の道中なのですが、それでもこの物語を青春小説としておすすめしたいのは、天衣無縫、荒唐無稽な師匠に振り回されながらも、師の圧倒的な俳句の才能を目の当りにし、どうして自分にはこの句の才能がないのだろうと苦悶しながら随行する曾良の姿が愛おしく、青春期特有のジタバタを感じてしまうからです。 道中を経て曾良が自問自答する「今回、俳諧まみれというより、俳諧しかない旅を通してわかったことがある。わたしは俳諧から愛されていない。だが…」のあとに続く言葉。ぜひ手に取ってお読みください。 (Y.M)
|
|
| 『乱歩と千畝』 | |
| 青柳 碧人/著 新潮社 「怪人二十面相」や「少年探偵団」など今でも日本中に愛される小説を生み出した探偵作家江戸川乱歩。第二次世界大戦中ナチスドイツに迫害されたユダヤ人たちにビザを発給し、多くの命を救った外交官杉原千畝。史実では二人の交流はありませんが、もし二人が出会って友人になっていたとしたら…。 学生時代に出会った二人は、浅草の地で語り合い、それぞれの道を歩んでいきます。友人となった二人が、戦前、戦時中、戦後どのように交流をしていくのか、歴史好きの方にも、乱歩と千畝のファンの方にも楽しめる一冊となっています。 (R.K)
|
|
| 『幕末維新史への招待 国際関係編』 | |
| 町田 明広/編 山川出版社 鎖国から開国へと転換し、国内でさまざまな政争が起こった幕末維新期。欧米列強による外圧は、日本に歴史的な画期をもたらしました。一方で、そのときの欧米列強ではなにが起きていたのか。また、日本の近隣諸国であった清・朝鮮・蝦夷・琉球とはどのような関係だったのか。世界の近代化は幕末の日本に何をもたらしたのか。国内政治からの視点だけではなく、海外からのグローバルな視点を交えて幕末維新期の国際関係に迫ります。日本史と世界史を融合した最新研究で幕末維新期の全体像をとらえ直した一冊です。 (S.M)
|
|
| 『昭和の名短篇 戦前篇』 | |
| 荒川 洋治/編 芥川 龍之介ほか/著 中央公論新社 歴史が大きく動いた「昭和」に誕生した数々の名作たち。芥川龍之介や中島敦など誰もが知る文豪たちの作品、全13篇を収録しています。 (A.K)
|