
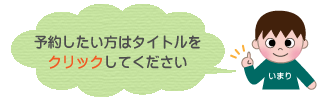
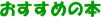
| 『日本語からの祝福、日本語への祝福』 | |
| 李 琴峰/著 朝日新聞出版 台湾生まれで芥川賞作家の李琴峰が、外国語である日本語をどのように習得したかを振り返った「語学エッセイ」です。文字の美しさに惹かれて中学2年の時に独学で日本語を勉強し、小説が書けるようになるまでの長い道のりが綴られています。しかし、ただの記録ではありません。本書の特徴は、学び始めの人がどのように日本語を見ているのかが詳細に書かれていることです。筆者が見たもの、感じたものを読むことで、私たちは普段意識していない日本語の面白さや不可解さを体験することができます。 (T.K)
|
|
| 『竜と蚕 大神坐クロニクル』 | |
|
アミの会/編 原書房 (S.S)
|
|
| 『おいしい推理で謎解きを』 | |
| 友井 羊・矢崎 存美ほか/著 双葉社 奥谷理恵は、フリーペーパー「イルミナ」の制作を手掛ける会社で働いています。職場に向かう足取りが重い早朝、芳ばしい香りに誘われ入ったのは「スープ屋しずく」。ジャガイモとクレソンのポタージュに感動した理恵は、それ以来「スープ屋しずく」の味が忘れられませんでした。 自分の化粧ポーチが職場で盗まれたこと、気が立った上司や後輩の冷たい態度、そして何よりも同僚を疑う自分に嫌気がさすこと…。「スープ屋しずく」の店主と料理たちはそんな理恵の悩みと疲れにそっと寄り添います。 美味しいたべものが導く、謎の真相とは。全4編の短編集です。 (A.K)
|
|
| 『サイコロだけで遊べる世界のゲーム』 | |
| 高橋 浩徳/監修 山と渓谷社 正六面体のサイコロは、紀元前2500年が始まりという説もあり、古くから使われてきました。この本ではサイコロだけを使ったゲームを紹介しています。中には丁半やチンチロリンなど時代劇に登場するものや、中国やアメリカ、ヨーロッパなどのゲームまで幅広く収録しています。またチップや筆記用具などの小道具を使うと、さらにゲームが楽しくなります。 最近ではボードゲームなどのアナログゲームが注目を集めており、サイコロの偶然性は計算力や駆け引きなどの判断力、出る目の確率まで、ゲームで遊びながら、学ぶことができる優れたものです。 (K.S)
|
|
| 『知識ゼロからのSNS・ネットトラブル対策』 | |
| 清水 陽平/著 幻冬舎 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、今や我々の生活には欠かせないものとなっています。日本では一憶580万人がSNSを利用し、娯楽だけでなく、インフラとして重要な役割を担っています。その一方で何気ない行為が、大きな悪影響を及ぼしSNSの投稿をきっかけに企業の社会的信用を失い、イメージ低下となり事業の継続自体が困難になるケースもあります。弁護士である著者は、企業のネットトラブルの実情を紹介し、気をつけなければならないポイントや、再発防止策を、事例をもとにイラストを交えてわかりやすく教えてくれます。便利なサービスとして利用できる時代だからこそ読んでおきたい一冊です。 (Y.K)
|
|
| 『考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常』 | |
| 青山 和夫・大城 道則・角道 亮介/著 ポプラ社 エジプトや中国、メキシコをフィールドに研究する外国考古学者たちの、嘘偽りのない忙しすぎる日常。ミイラを発掘したり、神々の怒りにふれ悪夢にうなされたり…と、波乱万丈、まるで映画のような研究生活かと思いきや? 嵐のような会議と怒涛の書類作成の日々、ダニや蚊、コブラとの闘い、灼熱の現場と断水の住居など、現実はもっと過酷でブラックな日常でした。 しかし、コツコツと研究を重ね、論文を書き学術的な成果をあげる毎日こそが、考古学者の楽しい日常なのです。 (Y.N)
|