
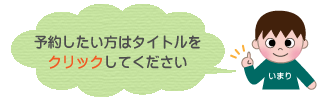
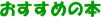
| 『新・古代史』 | |
| NHKスペシャル取材班/著 NHK出版 邪馬台国、卑弥呼、ヤマト王権など、日本の国の始まりは多くの謎とロマンに満ちています。この古代史の空白に迫るNHKスペシャル取材班は、最新の発掘調査と科学的分析に加えて、中国や韓国の国際研究に裏付けられたグローバルヒストリーの観点から、新たな解釈を紡ぎだしています。卑弥呼が三国志時代のパワーバランスを巧みに利用して、外交を有利に進めていたことなど、新たな歴史像の連続に、ページをめくる手が止まりません。 (T.K)
|
|
| 『福岡で始めるおとなの山歩入門』 | |
| 谷 正之/著 海鳥社 少しずつ春の気配が感じられる季節になりました。春の陽気に誘われて、この春は福岡まで足を伸ばして、山歩きなんていかがでしょうか。山を歩くと書いて「山歩(さんぽ)」。この本では、初心者にもわかりやすく、山歩の基本を写真とイラストを交えながら解説しています。 山歩において大切なのは「周りに迷惑をかけないこと」だと著者は語ります。そのために大切なのは事前の準備です。地図の読み方や服装と装備の整え方など、この1冊を読めば山への第一歩はバッチリですよ。 (A.K)
|
|
| 『すごい長崎 日本を創った「辺境」の秘密』 | |
| 下妻 みどり/著 新潮社 日本の西の果て、長崎。鎖国時代には日本で唯一の海外への窓口となり、異国情緒あふれる文化が醸成されました。多くの隠れキリシタンが密かに信仰を続け、非業の死を遂げています。そののち、原爆投下で一面の焼け野原になり、平和公園には観光客が押し寄せています。この街の記憶は、悲しみと苦しみに満ちたものでもあるのです。 いくつかの困難を乗り越えてきた人と街に魅了された著者は、まだ見ぬ大切なもの、語られていないものを探す旅へ。長崎という街に潜むものを呼び覚まし、寿ぎ、鎮めていく。「そんなすごい長崎」の案内です。 (Y.N)
|
|
| 『老いた親の様子に「アレ?」と思ったら』 | |
| 工藤 広伸/著 PHP研究所 突然やってくる親の介護。いつかくると分かっていても、漠然とした不安を抱えるだけでまだ何もしていない、という方も多いかもしれません。 この本の著者は、祖母や父親の介護を経験し、現在は東京の自宅から岩手の実家に通って母親の介護を12年以上続けています。その経験から、自分と同じ後悔をしてほしくないという思いで書かれた本です。「介護は親のためではなく自分のため」という言葉をキーワードに、自分だけで全てを抱えすぎない考え方を教えてくれます。 難しい介護保険制度等の知識はあえて省いた、介護のための基本のキ。軽く読める会話形式のこの本で、介護の準備を少しだけスタートしてみましょう。 (S.S)
|
|
| 『古代の酒に酔う』 | |
| 庄田 慎矢/編 吉川弘文館 少酒にまつわる考古学研究は世界各地で行われており、日本でも多くの資料や研究実例がありますが、物的証拠として酒そのものが残らない以上、どのような酒が飲まれていたのか、酒の醸造方法がいかなるものであったか、などについて深く掘り下げることは難しいことでした。そこで期待がかかるのが、醸造に用いられた可能性のある土器、甕です。 奈良時代の酒がどのようなものであったか検討するために、醸造実験用の須恵器の甕を製作し、平城京長屋王邸宅跡から出土した木簡レシピをもとに古代の酒造りに挑戦しました。酒造りに関する知識満載の一冊です。 (S.M)
|
|
| 『東京MUSEUM GUIDE』 | |
| 朝日新聞出版/編著 朝日新聞出版 楽しみにしていた企画展を見に、張り切っていく美術館も楽しいですが、ふらりと寄ってみて芸術に浸る時間も素敵です。本書では、東京都内の有名な美術館から、小さなアートギャラリーまで、様々なミュージアムを紹介しています。 日本一美しい本棚といわれる「モリソン書庫」を持つ東洋文庫ミュージアムや活版印刷の体験ができる印刷博物館など、眺めているだけでわくわくする記事に加え、美術館ならではの個性的なミュージアムグッズも載っています。居て、観て、買って楽しいミュージアム。多彩な楽しみ方を知ることができます。 (Y.M)
|