
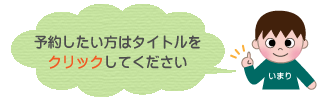
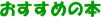
| 『蔦屋重三郎 江戸芸術の演出者』 | |
| 松木 寛/著 講談社 今、書店に行くとNHK大河ドラマ「べらぼう」の主人公、蔦屋重三郎のラッシュですが、この本はブームになる以前の1988年に出されていたものを新たに刊行したものです。小説ではなく、美術史家の視点で描かれた学術的な内容で、現在でも「蔦重」研究の柱とされています。作家や絵師の才能を見出し、独創的な企画力で、写楽や歌麿、馬琴らを世に出した江戸時代の名プロ デューサー「蔦重」はどのような人物だったのか。詳細な歴史資料をもとにその実像に迫ります。 (T.K)
|
|
| 『親への小さな恩返し100リスト』 | |
| 田中 克典/著 主婦と生活社 著者は、40年以上にわたって福祉の仕事に携わり、これまで500人の高齢者とその家族たちをサポートしてきました。親子の関係性に少しでも後悔がないように、100のリストで、無理のない介護のやり方を伝えてくれます。親は確実に老いていき、子がいつか恩返しをしたいと考えていても、そのタイミングを失うかもしれません。できなかった後悔をしないためにも、今できることをする、できるだけでいいと教えてくれています。 介護サービスに関する情報や解説もあり、いざ介護が必要なときに戸惑うことがない一冊です。 (Y.M)
|
|
| 『虫坊主と心坊主が説く 生きる仕組み』 | |
| 養老 孟司/著 名越 康文/著 実業之日本社 昆虫大好きの解剖学者である養老孟司さんと、コメンテーターとしても活躍中の精神科医、名越康文さんとの対談を収録した3番目の本です。ページをめくるごとに自然体で語る養老さんと分かりやすく解説を入れながら語る名越さんの掛け合いに引きこまれます。 取り上げている話題は、仕事や自分など、6つの身近なことですが、それぞれ静かに語りながら、解き明かしていきます。「これまでしゃべったことはお経みたいなものだから」と話される二人の対談を読んでいくと、だんだんと心までほぐれてくるような一冊となっています。 (K.S)
|
|
| 『きょう、ゴリラをうえたよ』 | |
| 水野 太貴/著 KADOKAWA 子どもの“いいまちがい”には、言葉の本質が詰まっています。 言語学を学ぶ著者が集めた、子どもたちの愉快で深い、いいまちがい。少ない語彙で、必死に考えた表現の数々は、日本語のルールの難しさを改めて感じ、文法の核心を突くものばかりでした。 いいまちがいには、言語の本質的な特徴と、人間の思考の仕方が多彩に含まれているそう。子どもの豊かな想像力は、言葉を拡張し、文化を創造する原動力になるのです。 さて、このタイトルのいいまちがい、子どもは一体、何を植えたのでしょうか! (Y.N)
|
|
| 『フリーランス農家という働き方』 | |
| 小葉松 真里/著 太郎次郎社エディタス 農家といえばその土地に根付いて暮らし、同じ作物を作るもの。そんなイメージを打ち破る、農地を持たない農家という働き方の提言です。 著者はかつて新聞社勤務だった女性。野菜の美味しさと農業の魅力にとりつかれてからは、農業の道へとまっしぐら。自分で農園を始めることが難しいと知ると、地域ごとに異なる農繁期に合わせて全国各地を飛び回る、フリーランス農家として生きると決めます。また、持ち前の積極性とコミュニケーション能力で、困っている農家とその助けになれる人を繋いでいきます。 これからの農業を明るく元気に支えたいという著者の思いが伝わる一冊です。 (S.S)
|
|
| 『人生が楽しくなる「シニア推し活」のすすめ』 | |
| 和田 秀樹/著 KADOKAWA 「推し活」という言葉がすっかり世間に定着した今、著者が伝えるのは「推し活」がもたらす幸せの効果です。心のときめきによる若返りの効果や仕事へのやる気、行動が活発になることで健康にも良い影響があるとされています。 実際に「推し活」によって人生が変わったという方のインタビューも掲載されています。シルバー人材センターでの保育の仕事を「推し活」とする、としこさん(80歳)は、世代を超えた交流のおかげで生き生きとした毎日を送っていらっしゃいます。子どもたちとの時間が何よりも喜びなのだそう。 幸せがあふれる1冊です。 (A.K)
|