
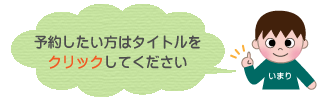
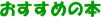
| 『はたらく物語』 | 『そして誰かがいなくなる』 | |
| 河野 真太郎/著 笠間書院 働くことは私たちの生活に大きく係わっています。生計を立てる、新たな技術や知識を身に付け自己成長によって充実感を得る、社会貢献などが労働の定義として挙げられますが、その意味や考え方は人それぞれで多様です。そんな中で、ほとんどの人が「働くこと、労働を、自分のものにしたい」という願望があるのではないかと著者は提言しています。そこで、マンガやアニメ、映画の作品を通して、現実世界での労働や働き方の問題に目を向け、その願望を実現へと導く方向性を示してくれています。 (Y.O)
|
下村 敦史/著 中央公論新社 大人気覆面小説家が山奥に建てた洋館のお披露目会が行われることになり、若手作家や文芸評論家たちが館に集められました。何故自分たちがお披露目会に呼ばれたかもよく分かっていない参加者たちを尻目に、それまで誰にも姿を知られていなかった覆面小説家が姿を現します。そして、その人物が発した一言で、参加者たちは次第に疑心暗鬼に陥っていきます。 最後の驚きの展開により現実と物語がリンクする、衝撃の本格推理小説です。 (S.S)
|
|
| 『なぜあの人と分かり合えないのか 分断を乗り越える公共哲学』 | 『長崎の教科書 大人のための地元再発見シリーズ』 | |
| 林 茂/著 熊本日日新聞社 なぜ、あの人と分かり合えないのだろう。お互いの溝が埋まらずに議論が平行し、対立する意見の相手を「分からずや」と非難し…。 社会が分断する議論よりも、相手の理論構造をまずは理解するスタンスを広めましょう。そのために、問題を問題としてとらえるための枠組と、いくつかの観点が必要です。 これが“公共哲学”の手法。さまざまな理由を言語化し、さまざまな選択肢をフェアな形で議論の場に提供します。 身近にあふれる「決着がつかない課題」について考えはじめたら、それはまさに「公共」を「哲学」していることのスタートです! (Y.N)
|
JTBパブリッシング 本書では、理科・社会・国語・美術と家庭科・算数の5項目に分けて、歴史・産業・郷土料理など長崎県にまつわる様々な情報を豊富な図や写真を交えながら、詳しく紹介しています。理科の項目では、島が多く、海岸線が長い地形がどのように今の形に変動していったかや、五島列島の成り立ちなどを知ることができます。また、社会の項目では、佐賀県も長崎県だった時代のことについても書かれており、長崎県の沿革を詳しく知ることができます。 他にも、人口の統計や略年表が掲載されています。長崎のことを知りたい人にとって良い教科書となっています。 (M.O)
|
|
| 『夜更かしの社会史 安眠と不眠の日本近現代』 | 『大災害とラジオ』 | |
| 近森 高明,右田 裕規/編 吉川弘文館 ついついやってしまう「夜更かし」。翌日、欠伸を堪えながら仕事へ…なんて経験のある方も多いのではないでしょうか。 夜間の行動において大きな変化をもたらしたのは、なんといっても「電気」の発明です。灯りがともったことで人間の行動時間が大幅に伸び、働き方や生活パターンが多様化していきました。本書では「眠らない工場・街」の登場にスポットを当て、「安眠」に対する社会の変化について詳しく解説されています。社会自体が24時間化していく中で、私たち人間はどのように「いつ眠るか」「いつ起きるか」を自制しているのでしょうか。 (A.K)
|
大牟田 智佐子/著 ナカニシヤ出版
災害時にラジオが求められるのはなぜか。テレビの「地震記者」時代に阪神・淡路大震災を迎え、その後も「災害報道専門記者」としてラジオ報道に携わった筆者は、ラジオの「共感放送」という特性に注目しました。リスナーの置かれた状況に寄り添い、共感しながら励ましや音楽などを提供する「共感放送」は、復興のエネルギーを引き出し、被災者の背中を押すことができると筆者は考えます。 現在のラジオ番組の形態が生まれた背景や、様々な事例をもとに災害放送について分析し、災害放送におけるラジオの役割を解明します。 (S.M)
|