
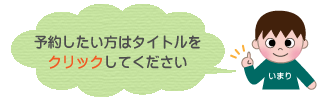
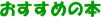
| 『あまカラ食い道楽』 | 『生きるとはどういうことか』 | |
| 谷崎 潤一郎 ほか/著 河出書房新社 関西の伝説の月刊誌『あまカラ』。戦後間もない頃、京都の老舗和菓子店、鶴屋八幡がスポンサーになり、刊行されていました。日本を代表する文人や著名人たちによる、舌鼓垂涎の随筆が並んでいたのです。 これは、その中から選りすぐりのものをまとめたもの。東西卵焼きについて熱く討論した話や人生の中で一番うまかった弁当の思い出などなど。 人は“食”について語りだすと、こうも多弁になり、幸せな気分になるのでしょう。究極の食エッセイ集です。 (Y.N)
|
養老 孟司/著 筑摩書房 著書「バカの壁」で知られる医学博士で解剖学者の養老孟司さん。 本書には、2003年からこれまでの間に執筆された随筆が、「生きるとは」というテーマを軸に、人生・環境・身体など様々なジャンルに分け収められています。自然や解剖の世界を通して語られる人生観は、広い視野で物事を達観する魅力に溢れ、時にユーモアを交え、あらゆる事に対する、ものの見方や考え方が語られます。 日常の中にある思考の視点が変わる一冊です。 (K.A)
|
|
| 『深海ロボット、南極へ行く』 | 『犬が看取り、猫がおくる、しあわせのホーム』 | |
| 後藤 慎平/著 太郎次郎エディタス 「後藤さん、南極用のROVってつくれる?」 南極の生態系研究者からの一言で、ROV(水中ロボット)の工学博士だった著者は、南極の湖底調査のためのROV開発とともに、南極観測隊にも参加することになります。 限られた予算と期間内での開発、南極での野宿に向けた訓練…。数々の苦難を乗り越え辿りついた南極では、チームの食糧が行方不明になったり、寝泊まりしていた小屋が暴風で浮いたりと、数々のトラブルに見舞われます。 観測隊メンバーの優しさに支えられながら、子どもの頃から憧れていた南極で湖底調査を行う体験記です。 (S.S)
|
石黒 謙吾/著 光文社 人間の死を看取る犬や猫がいます。老人ホームで、最後の時を迎える老人たちのベッドに寄り添い、身体を擦りつけ、顔を舐め、傍で静かにおくる犬の姿に心が揺れます。 本書は、ホームでの11年間にあったエピソードが写真と共に綴られています。そこには、このホームでの取り組みを多くの人に知ってもらい、老人ホームの理念、実態、課題、老人福祉のこと、動物保護問題など、関心を持ってほしいという著者の思いが込められています。このホームでは、たくさんの胸を打つ物語が紡ぎ出され、奇跡的な出来事が起こっています。 (Y.K)
|
|
| 『古代ギリシアの日常生活』 | 『Dr.モルック』 | |
| ロバート・ガーランド/著 田口 未和/訳 原書房 あなたが、もし紀元前420年の古代ギリシア、アテナイ(現在のアテネ)にタイムスリップしたらどんな生活が待っているでしょうか。この質問に答えるように、この本で紹介されているのは、当時のアテナイで暮らす人々の衣食住など身の回りの事柄です。市民でいることがフルタイムの仕事になったり、兵役や、奴隷制度があったり、男尊女卑の考え方が社会的に認められていたりと、現代社会に比べると驚くことばかりです。しかし、この頃には演劇の鑑賞やオリンピックの基になる競技会はすでに存在していました。遠い昔の古代ギリシアが、グッと身近に感じられることでしょう。 (K.S)
|
ハツ賀 秀一/著 心書院
長さ20cmほどの木の棒を投げ、スキットルと呼ばれる1から12の番号が表示されたピンを倒して、ぴったり50点を取っていくモルック。フィンランドで開発されたスポーツです。小児科医の著者はフィンランドに留学した際にモルックと出会いました。競技の内容はもちろん、それ以上に年齢や性別、国籍を越えて多くの人々と交流ができる楽しさや喜びを体感しモルックに魅了されます。やがて、日本に広める活動を始め、日本モルック協会を設立。今や競技人口は100万人で、来夏には函館で世界大会も開催予定です。 自身の生涯をふりかえりながら、モルックの面白さとモルックを通して医師として貢献できることを考え、その思いを伝えています。 (Y.O)
|