
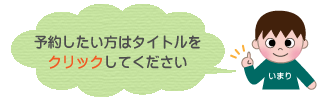
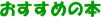
| 『ヘルシンキ生活の練習』 | 『ぼくとがんの7年』 | |
| 朴 沙羅/著 筑摩書房 コロナ禍のヘルシンキで、仕事をすることになった。子どもを二人つれて・・・。 日本国籍をもつ在日コリアンの社会学者が、暮らしてみて感じた、日本との違いの数々。それは習慣や食べ物だけではなく、教育や社会福祉の在り方、幸福の感じ方でした。 ヘルシンキで出会った人々から教わったことや助けられたことは、生きていく上でもかけがえのないものばかり。国家と制度は、人それぞれの幸せを支えるために存在していることを深く認識させられます。 (Y.N) |
松永 正訓/著 医学書院 小児外科医である著者が患者として、膀胱がんと向き合ったことを綴った闘病記です。医師として知識を持ちながらも担当医の発言に不安になることもあったようです。病の恐怖を感じ、家族を残して亡くなってしまった時のことを考えたり、鬱になったりしながらも、奥さんの手を借りながら乗り越えていく様子が書かれています。 巻末には、がんを経験して学んだことや、患者側から見た医療の改善点が書かれています。また、がんを患って死を恐れたり、悩んだりすることへの著者の考えも紹介しています。 (M.O) |
|
| 『はなちゃんのみそ汁 青春篇』 | 『かわいい我には旅をさせよ ソロ旅のすすめ』 | |
| 安武 信吾/著 安武 千恵/著 安武 はな/著 文藝春秋 「食べることは生きること」を心得としていた母・千恵さんはがんを患い、自分がいなくても子どもがひとりで生きていけるようにと5歳の娘のはなちゃんにみそ汁作りを教えました。そんな家族の日々の様子を綴ったブログをもとに「はなちゃんのみそ汁」という作品が書籍化や映画化され反響を呼びました。それから10年、大切な人を失った父と娘は、互いに慈しみ時には反発しながら時を過ごしてきました。その暮らしぶりと父娘それぞれの心情を往復書簡の形で語っています。 18歳になったはなちゃんの姿は千恵さんにどう映っているのでしょうか。 (Y.O) |
坂田ミギー/著 産業編集センター 著者は、一人旅のおかげでストレスが発散され、ひねくれた性格が「まし」になり、教養が深まり、失恋の傷が癒え、結婚相手も見つかり、うつ病がよくなり、あこがれの仕事に就くことができました。誰もがこんな効果を受けるとは限りませんが、日常を離れ、たった一人で旅をする、そんな体験は多かれ少なかれその後の生き方に影響があるのではないでしょうか。 一人旅をしてきたから生きてこれたという旅マニアの著者が、たくさんの旅の中から、特に印象に残ったことを紹介し、自分の生き方がどう変わったかを書いた本です。 (N.K) |
|
| 『図説 世界の水中遺跡』 | 『国境を超えたウクライナ人』 | |
| 木村淳、小野林太郎/編著 グラフィック社 世界中に歴史的遺跡は数多ありますが、海の中にも多くの遺跡が存在しています。人の目に直接触れないため、知名度は低いものの、水の中では影響を受けにくく、今でも当時の様子を残しているものも存在しています。この本では世界中の海で見つけられた水中遺跡を、美しい写真で鑑賞することができます。 1281年、元寇で伊万里湾の鷹島周辺にモンゴル軍の船が停泊し、暴風雨により多くの船が沈没したとされる「鷹島海底遺跡」も貴重な遺跡の一つとして紹介されています。 副題にもありますが、水底に眠る「時の証人」として、水中遺跡は様々な歴史を後世の私達へと語りかけているようです。 (K.S) |
オリガ・ホメンコ/著 群像社 著者はキエフ生まれ。東京大学大学院で博士号取得、現在はキエフ・モヒラ・ビジネススクール助教授。ウクライナ生まれで国外で活躍した人は多く、作曲家のプロコフィエフや昭和の大横綱大鵬はウクライナ人の父を持ちます。本書は、国境を越えたウクライナ人として、著者が日本に伝えたい10人を紹介したものです。ウクライナ人にとって「国境」とは何なのでしょう。国境に対して「不安」と「自由」という相反する感情を持つウクライナ人。ウクライナはつねに自分たちの土地を守る必要がありました。トルコ、ポーランド、オーストリア、ドイツそしてロシア。様々な国に占領された過去をもち、今も戦禍の中にあるのです。自由思想家のスコヴォロダーや空飛ぶ夢を実現したシコールスキイ等。異郷の地で活躍した人々を知り、ウクライナを知ってほしいと著者は願います。 (T.M) |