
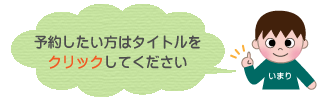
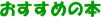
| 『エジプトの空の下』 | 『まんが訳 稲生物怪録』 | |
| 飯山 陽/著 晶文社 2011年、イスラム教研究者の著者は夫と1歳の娘を連れてエジプトに住むことになります。まさに「アラブの春」と呼ばれる政治的動乱期の首都カイロに降り立ったのです。そこでは奇妙な出来事や危険な事件が次々と起こります。本書は研究者としてではなく一人の人間として、当時のエジプトの様子や日常生活を綴るエッセイです。「ピラミッドを破壊せよ」「ファラオの呪い」「エジプトのアルカイダ」等、全10章からなる内容は「アラブの春」で言われた「民主化」や「自由」とは全く違っていたと著者は語ります。 今でもイスラム国との戦いが続くエジプトでは、若い兵士がテロとの戦いに投入されています。エジプトの革命をクーデターと決めつけず、私たちには別にすべきこと、できることがあるはずと著者は訴えます。 (T.M) |
大塚 英志/監修 筑摩書房 備後国(現在の広島県)を舞台に当時十六歳の武家の子息、稲生平太郎(いのうへいたろう)の屋敷でおこる物の怪たちの姿を描いた絵巻『稲生家妖怪傳巻物』。もちろん絵巻なので、一枚の絵に文章が添えられているものなのですが、本書では、その絵を拡大縮小やコマ割りをして、マンガのように読み進められるよう翻訳しています。不思議なことにこのまんが訳でよむと、内容がさくさく頭の中に入ってきて、静止画の登場人物が動き出すように見えてきます。古典を原作にした漫画はありますが、本書は絵巻の絵そのものを現在の楽しみ方で読むことができるので、当時の人々がどのように絵巻物を楽しんでいたのかを感じることができます。 (Y.M) |
|
| 『珍電子楽器LOVE』 | 『職場のトリセツ』 | |
| オオハシヒロミチ/著 リットーミュージック 本書には、シンセサイザーやリズムマシンなど100種類以上の珍しい日本の電子楽器が著者の解説と共にカラーで収録されています。過去の人々が思い描いていた未来像のことを指す「レトロフューチャー」という言葉がありますが、この珍電子楽器の多くは70年代~80年代に製造されたものです。未来への夢にあふれた、可愛くもハイセンスな珍電子楽器のレトロフューチャーなデザインは、まるでSF映画の世界に迷い込んだようで、見ているだけで楽しくなってきます。 付属する珍電子楽器の演奏CDも必聴です。 (K.A) |
黒川 伊保子/著 時事通信社 人工知能研究者として40年近く人間の感性を見つめ続てきた著者が、人によってどのような考え方や行動の違いが出てくるのか詳しく説明しています。 人間の脳には「とっさに優先して使う神経回路」があり、ひとによってちがうため、誤解が生まれ、職場での人間関係のもやもやの原因になっているそうです。 上司と部下でも考え方が違ってきます。違う感性の人と職場で、どのような対応をしていけばいいか対処法を見つけ出せるかもせれません。 (M.O) |
|
| 『人の研究を笑うな』 | 『食べる経済学』 | |
| 藤田 紘一郎/著 ワニ・プラス 著者は「カイチュウ博士」として知られ、寄生虫学や熱帯医学、感染免疫学を専門とする医者として、50年以上にわたる研究者人生を歩んできました。今年5月に81歳で逝去。生前、80歳の節目に自身の人生を振り返り、奇想天外なエピソードをユーモアたっぷりに紹介したものです。インドネシアを始めとする海外での波乱に満ちた出来事や、15年間サナダムシをお腹で飼い続けた話など…。 日本人の過剰な清潔志向を憂いながら、健康について改めて問い直してほしいとの願いがこめられています。 (Y.O) |
下川 哲/著 大和書房 食べることは私たちにとって最も身近で不可欠な行動です。技術の進歩やグローバル化などにより選択肢が増え、何をどう食べるのが正しいのかを理解することが難しくなっています。たいていの人はおいしものを安く食べたいと思い、できれば安全で体に良いものをと望みます。それだけでよいのでしょうか? 個人の栄養面と、地球全体の環境問題を同時に改善するために「健康的で持続可能な食生活」の基準が専門家グループによって提案され、世界的に広まっています。そうした社会の動きを理解し、個人の食生活を見直すきっかけとなる一冊です。 (N.K) |