
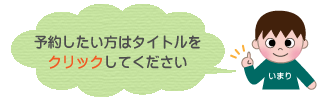
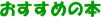
| 『土になる』 | 『世界ピクト図鑑』 | |
| 坂口 恭平/著 文藝春秋 作家、画家、音楽家として活躍する著者は貸農園で農作業を始め、毎日のルーティーンの中に畑仕事が加わりました。畑に入ると野良猫がやってきて寄り添う。虫と目が合う気がする。土は喜んで出迎えてくれているような気がする。野菜も確実に成長している。周りには支えてくれる人がいる。 そんな日々の中、心身ともにどんどん楽になっていき自分で自分を癒せているという実感があり、10年来の躁うつ病から解放されました。日々の作業を綴る農業日誌でもあり、自然や自分を深く見つめる哲学書でもあります。 (N.K)
|
児山 啓一/著 ビー・エヌ・エヌ オリンピックで話題となったピクトグラム。ピクトグラムの始まりは紀元前3200年頃、古代エジプトやメソポタミアの時代と言われています。そこから長い年月をかけて進化し、言語や風習が異なる人々でも、共通の認識を持つことができる記号として世界中で使われるようになりました。 日本の歩行者用信号を見ると、人間が止まったり歩いたりしているピクトグラムが描かれていますが、イギリスには馬が描かれている信号があることをご存知ですか?その国ならではの特徴も見えてとても面白いですよ。 (A.K)
|
|
| 『ぼくらはひとつ空の下 シリア内戦最激戦地アレッポの日本語学生たちの1800日』 |
『世界を大きく変えた20のワクチン』 | |
| 優人(アフマド・アスレ)/著 小澤 祥子/取材・文 三元社 著者はシリア・アラブ共和国アレッポ生まれ。シリアで戦争による荒廃した地域社会や女性、子どもたちのサポート体制を整えるプロジェクトに携わり、日本センターで日本語を学び日本人との交流も深めてきました。2011年、今世紀最悪の人道危機と呼ばれるシリア内線が始まり人々の生活は一変、アレッポでも戦闘や爆撃により多くの命が奪われました。自分の命も危険な中、著者は日本語を勉強し続けます。苦難の時代において学ぶことは「希望」になりました。本書は内戦が始まる前と後の両方の、日本語学生と日本人との交流や絆についての1800日の記録です。最大の激戦地アレッポで日本語が熱心に学ばれている現実は、未来のために学び続けることの意義を訴えます。 (T.M)
|
斎藤 勝裕/著 秀和システム 2019年末に新型コロナウイルス感染症が発症し、世界を震撼させました。二年経過しましたが、未だに私たちはその脅威の中での生活を余儀なくされています。出口の見えないトンネルの中に追いやられている気分での生活に、一つの光が差したのがワクチンの開発と接種。それにより、感染の発症予防や重症化予防の効果が高いと言われています イギリスの医師が天然痘予防に用いたワクチンが最初で、ワクチンには220年の歴史があります。本書ではその歴史を紐解きながら、ワクチンの有効性や開発の裏側を解説しています。ワクチンの知識や感染症を理解することから、感染症予防に取り組むことの大切さを教えてくれます。 (Y.O)
|
|
| 『ウチダメンタル 心の幹を太くする術』 | 『ばにらさま』 | |
| 内田 篤人/著 幻冬舎 14年間プロサッカー選手として日本とドイツで活躍してきた著者が今までの経験や先輩や同僚たちを見てきて感じたこと、考えたことを踏まえて、多くの怪我やプレッシャーの中でどのようにメンタルを上下させないようにしていたか紹介されています。 本書では、現役時代の話、中田英寿さんとの対談などが収録されていて、貴重な話を知ることができます。著者が経験から培ったメンタルの安定方法はサッカーをしている人だけでなく、先行き不透明な社会に生きている私たちの参考になることでしょう。 (M.O)
|
山本 文緒/著 文藝春秋 主人公の広志は、就職したばかりのサラリーマン。同僚の瑞希という恋人もできて、二人の交際は順調かと思われましたが、クリスマスを境に二人の関係は徐々に冷え込んでいきます。その時、広志が下した結論とは…? 終盤のほんの1行でひっくり返される世界観。思わず二度読みすること請け合いです。このほかにも、ついつい夢中になってしまう短編6話が掲載されています。 (A.K)
|