
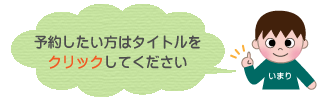
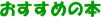
| 『立花隆 長崎を語る』 | 『レインメーカー』 | |
| 長崎文献社編集部/編集 東京長崎文献社 立花隆が長崎市出身ということをご存知ですか。生まれたのは長崎医科大学付属病院産婦人科病棟。ここは8月9日の原爆で一瞬にして廃墟と化しましたが、この廃墟を「僕の生まれた場所」と語りました。本書のテーマは立花隆の原点を問いかけ、「長崎」が原点だという証を読者に知ってほしいこと。そして生涯のテーマと考えた「戦争と平和」です。「立花隆長崎を語る」「私が会った立花隆の実像」「立花隆の家族史」の全3章では、原爆資料館での講演録や原爆論、立花隆の好奇心や無名時代からの実像、そして自身のルーツを長崎に求める理由など。 「平和へのゆるぎない思いを長崎は立花さんと共有している」という長崎市長の言葉は、若い人たちへ伝えることを大切にした立花隆の思いと重なります。 (T.M) |
真山 仁/著 幻冬舎 法律事務所の所長、雨取誠は医療事件を扱う弁護士です。急患の2歳児の男の子を搬送先の病院が助けられなかったことに対して、遺族が訴訟を起こした事件を担当することになりました。医療過誤は本当に起きたのか、意見が食い違う両者ですが、雨取の弁護はどんな展開を見せるのでしょうか。 裁判での病院側と遺族側との攻防戦や、病院側、遺族側、弁護士側それぞれの思惑、緊迫した治療の様子が克明に描かれており、医療の現場を垣間見ることができます。また、日本の医療現場が抱える問題についても触れられていて、知られざる世界に目を開かせてくれる一冊です。 (M.O) |
|
| 『人生100年時代の脳科学』 | 『1万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き』 | |
| 中村 克樹/著 くもん出版 「人生100年時代」という言葉をよく耳にします。世界で急速に長寿化が進み、今後は寿命が100歳までのびると想定され、それを見据えた人生設計が必要とされています。100歳まで生きると考えると誰しも健康でいたいと願うもの。そこで、長年脳科学の研究に取り組んできた著者が、その知見から健康寿命を延ばすことに役立つ情報を本書で提供しています。睡眠や食事など私たちの生活と脳がいかに密接な関係があるかをユーモアを交えてわかりやすく紹介されています。脳の働きを知ることで心身共に元気になれる一冊です。 (Y.O) |
加藤 俊徳/著 ダイヤモンド社 左利きの人は10人に1人と言われていますが、そのメカニズムについてはあまり解明されていませんでした。著者は生まれつき左利きで、幼いころから「なぜ、みんなのように右手が上手に使えないのだろう?」と感じ、その疑問を持ち続け、世界で最初の脳内科医となりました。 この本では、脳のMRI画像や図を使って、左利きと右利きの違いについてわかりやすく解説しています。さらに、スポーツには左利きが有利か、子どもの左利きは矯正したほうがいいか、などにもアドバイスを与えています。 (N.K) |
|
| 『ミルクとコロナ』 | 『7.5グラムの奇跡』 | |
| 白岩 玄 ・山崎 ナオコーラ/著 河出書房新社 同じタイミングで文藝賞を受賞し作家としてデビューした、いわば同期。しかも、ふたりにはともに、育児中という共通点がありました。そこで始まった、往復の育児エッセイ。 しかし、父親の目線と母親の目線、覚悟の芽生え方や子どもとの関わり方に違いがあって、それはそれで考えさせられて……。 アンダーコロナ、アフターコロナと2部構成。これからの「ニューノーマル」の世界で育児はどう変化していくのでしょうか。それぞれの家族の、物語のようなエッセイです。 (Y.N) |
砥上 裕將/著 講談社 誰かの瞳を見つめていることが好きという感覚を持っていた野宮は、瞳に関する仕事があることを知り、視能訓練士になりました。街の小さな眼科医院で働き始めますが、要領が悪く不器用で自分に自信がない彼は悪戦苦闘の連日です。しかし、院長や医院の先輩スタッフ達の働く姿を見て学び、未熟ながらも患者さんとしっかり向き合い、優しく寄り添うのでした。彼が視能訓練士という仕事を通して成長していく様が生き生きと描かれています。また、見えるということが当たり前ではなく、実に奇跡だと改めて気づかされる小説です。 (Y.O) |