
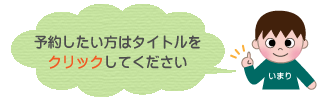
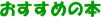
| 『世界を変えた100のシンボル 上・下巻』 | 『地域ごはん日記 おかわり』 | |
|
コリン・ソルター/著 甲斐 理恵子/訳
原書房 東京オリンピックで話題になったスポーツ競技のピクトグラム。それぞれの競技の特徴を捉え、シンボル化しています。 紋章・マーク・文字・記号・デザインなどこの本で紹介されている100のシンボルも、よく見かけるものばかりで、普段の生活の中で使用されているものもあります。どのシンボルにも形や色に由来があり、出来上がるまでの経緯も様々です。また「卍」の模様は、太古から幸運のシンボルとして伝わっていたものが、たった25年間で忌み嫌われるものに変わってしまったという例もあります。 誰にでも意図を伝えられるシンボルがどのようにできたのか。その秘密に迫る一冊です。 (K.S) |
山崎 亮/絵と文 建築ジャーナル
このまちの、この店。あの方の、あの味。世界中を旅して出会った「地域ごはん」の数々。そのまちで奮闘する人々を支えるのは、そのまちならではの、愛される味でした。 コミュニティデザインやまちづくりなどを専門とする建築家が、食べながら地域の未来について考えます。新しいものと古いもの、変えるべきものと変えざるべきものなど、答えの出ないまちの課題は、なかなか難しいものばかりです。 人との出会いとつながりの中に、おいしいきっかけや思い出があること。それが何よりも素敵に思えてきます。 (Y.N) |
|
| 『喫茶とまり木で待ち合わせ』 | 『今日拾った言葉たち』 | |
| 沖田 円/著 実業之日本社 お店のドアを開けると、心の波を穏やかにするようなコーヒーのいい香りが漂う、そんな「喫茶店とまり木」に集まる人たちのお話です。何気ない日々の生活の中で様々な想いを抱えて暮らす人々の様子が描かれています。 5編からなる連作短編小説を、読み進めていくうちに、読み手自身もこの喫茶店の片隅に座って、店主が淹れてくれたコーヒーを味わいながら日常を忘れ、気持ちが休まるような感覚になっていきます。 (Y.K) |
武田 砂鉄/著 暮しの手帖社 雑誌「暮しの手帖」にて2016年から続く連載をまとめた本書には、タイトルにもあるように、新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・SNSなどから著者が拾い上げた言葉をもとに、現代に起きる様々な出来事を見つめた、評論や書き下ろしエッセイが収められています。 些細な事から話題になった事まで、ひとつひとつの言葉を幅広く丁寧に掘り下げ、考え接していく著者の姿勢から、発せられた言葉の裏にある本質や受け取る側の思慮深さの大切さを感じる一冊です。 (K.A) |
|
| 『あらゆる薔薇のために』 | 『66歳、動物行動学研究家。ようやく「自分」と いう動物のことがわかってきた。』 |
|
| 潮谷 験/著 講談社 「オスロ昏睡病」という難病の元患者である京都府警の八嶋警部補は、事件の捜査のため、以前世話になったことのある『はなの会』の施設に向かいます。オスロ昏睡病の患者や、患者の家族が交流するための団体『はなの会』で、学生時代、同じ元患者の涼火と付き合っていた八嶋は、十二年前、突然死んでしまった彼女との思い出を回想しながら捜査を進めていきます。オスロ昏睡病関係者を狙った連続殺人事件には、快復した患者の身体の一部にできる、薔薇の形をした腫瘍の謎が関わっているようで…。捜査をする中で八嶋は、涼火が命を落とす前の異変が、薔薇が見せる白昼夢によるものだと気づきます。元患者たちが見る白昼夢は何を表しているのか、難病治療がもたらした闇に挑みます。 (S.M) |
竹内 久美子/著 ワニブックス 「神経質で要領が悪く取りこし苦労が多い。挙句、人生で何度もメンタルが崩壊した…。」著者は自身のこれまでを振り返り、勉強にしても人との係わりでも挫折の連続だったと語ります。そんな中でも、勉強の面白さに気づいたこと、自分を認めてくれる生涯の友を得たこと、そして恩師の日高敏隆氏との出会いによって道が開かれたことなど人生の転機に触れ、改めて自分自身を読み解いています。 動物行動研究家、そして人間としての「自分」は著者の眼にどう映ったのでしょうか。 (Y.O)
|