
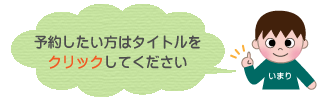
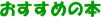
| 『83歳、脱サラ農家の終農術 おいしく・はつらつ・愉快に生きる』 | 『あくてえ』 | |
杉山 経昌/著 築地書館 著者である杉山氏は1990年50歳の時に脱サラし就農しました。外資系サラリーマンとして働いた知識を武器に、就農4年目にして農業経営者として独立する目途が立ち、この地で一生を過ごすことを決めます。そして78歳、農地を後継者に引き渡し、農業ビジネスを継承、終農。83歳である現在は、農家時代に築いた人間関係や数多くの趣味に支えられ、充実したリタイアメント・ライフを送っています。 本人が「天国の上をいく極楽」というほどの引退後生活を紹介しながら、幸せな老後を送るための方法を伝授します。 (A.K) | 山下 紘加/著 河出書房新社 小説家志望の19歳のゆめは、母と90歳になる父方の祖母との三人暮らし。父は不倫をし母と別れてから別の家庭を作り、都合のいい時だけ連絡をしてくる始末。ゆめは毎日悪態をつく祖母にイライラし、些細なことで二人の言い争いが勃発します。祖母の前では「ばあちゃん」と呼びつつ、陰では「ばばあ」と侮蔑を込めて呼び、ゆめ自身も悪態をつくのでした。 祖母の介護、気弱で優しすぎる母への気遣いでゆめは苛立ちとやりきれない毎日を過ごしています。小説家の夢を追い続けながら、いびつな家族の現実で生きるゆめの姿を愛おしく感じます。 第167回芥川賞候補作。 (Y.O) | |
| 『猿蟹合戦の源流、桃太郎の真実 東アジアから読み解く五大昔話』 | 『その本は』 | |
| 斧原 孝守/著 三弥井書店 「猿蟹合戦」「桃太郎」「舌切り雀」「かちかち山」「花咲か爺」という日本昔話を代表する五つの話の源流を探ります。いかにも古くから伝わっていた日本独自の話のように見えますが、文献で確認できるのは江戸時代半ばまでで、特徴的なストーリーの由来についてはほとんど分かっていません。 登場するキャラクターや物語の構成、話の背景を、日本各地に伝わる類話や、東アジアの諸民族に伝わる類話と比較することで、昔話の中でどこまでが普遍的な部分で、何が日本的な変化であるかを解明していきます。国外の昔話を楽しむとともに、今までの日本昔話の考え方が変わる一冊です。 (S.M) | 又吉 直樹・ヨシタケシンスケ/著 ポプラ社 本が大好きな王様が二人の男に命じました。世界中の“めずらしい本”について、知っている者を探し出し、話を聞いてくるように、と。やがて旅にでたふたりは、たくさんの本の話を持ち帰り王様のために、夜ごと語り始めます…。 足が早すぎて、タイトルを読むことがやっとの本の話。ある日、宇宙から送られてきた、読んだ人が必ず不幸になる謎の本の話。絵本作家を夢見る二人の、キュンとする交換日記の話。 芥川賞作家で芸人の又吉直樹と、人気絵本作家のヨシタケシンスケがタッグを組んだ、本にまつわるショートショート。本が好きな二人が王様に語りだす“めずらしい本”の話の、意外な (Y.N) | |
| 『子どものこころがそだつとき 子育ての道しるべ』 | 『トラりんと学ぶSDGsと博物館』 | |
| 笠原 麻里/著 日本評論社 本書では、長きに渡り精神科医として子どもに寄り添ってきた著者が、子どもがつまずいた時に大人たちが知っておくべきことを紹介しています。 著者が多くの子どもたちやその親、教員の話を聞いた経験から、不登校や発達障害などの様々な症例を挙げ、それが起こるまでの成長・発達について詳しく解説しています。 大きな問題もなく学校生活を過ごしてきた子どもが、急に不登校になってしまうことは珍しくありません。子どもたちの成長過程について、じっくり考えてみませんか。 (M.O) | /京都著 集英社 最近よく目にしたり聞いたりする「SDGs」。 「持続可能な開発目標」と訳されるこの目標は国連が提唱し、今、世界中で取り組まれています。 京都国立博物館のPR大使「トラりん」と栗原副館長が、17の開発目標の一つひとつを解き明かし、博物館や美術館で出来ること、実施していることを解説していきます。 二人の会話形式で、ほのぼのと話が進められるなか、世界の現状と個人で出来ること、覚えておいたほうが良いことなどがしっかりと説明されています。 (A.K) |