
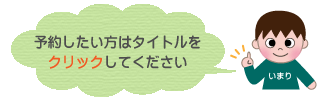
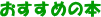
| 『いのちの人形』 | 『仕事論』 | |
|
横関 大/著 KADOKAWA マンションの一室で服毒死したとみられる男性の遺体が発見されますが、鑑識の到着前に厚生労働省の役人を名乗る男達が現れ、警察は彼らに事件を横取りされてしまいます。不審に思った捜査一課の川村は、サイバー犯罪捜査官の高倉と男達のことを調べていくと、28年前に政府が秘密裏に作った“ドールズ”という組織だということが判明し、さらに同じ時期に生後間もない7人の赤ちゃんが、ある教授のもとから保護されていることがわかります。 すべてが繋がったとき、全世界が驚愕するような事実を彼らは知ることになるのです。 (Y.U)
|
藤村 忠寿・嬉野 雅道/著 総合法令出版
北海道ローカル局からスタートし、大ヒットしたバラエティ番組『水曜どうでしょう』。その名物ディレクターである著者2人が、仕事に対する考え方などを語っています。 どんな仕事にも共通するのは、長い経験を元に蓄積される説得力。「居心地の良い場所は自分で作る!」と、快活で正直に語られる内容は、ときに耳が痛くもあり、ときに肩の力を抜いてくれます。 今の仕事に悩みを抱えている方、春から新社会人になる方などにおすすめしたい一冊です。 (M・T)
|
|
| 『発現』 | 『マイ遺品セレクション』 | |
|
阿部 智里/著 NHK出版 大学生のさつきは姪っ子である「あやね」に会って以来、不可解なものを見るようになりました。兄、大樹も同じような現象に悩まされ、我が娘を見ることが怖いと言い出します。次第にさつきも“恐ろしい何か”の影響を強く受けるようになり、兄妹は揃って入院することに。彼らに見えているもの、それは眼窩が黒くぽっかりと空いた少女の姿でした。
十数年前の母親の死は、この現象と関係があるのか、なぜ父親には少女が見えないのか、調査を進めるうちに見えてきた血縁関係…。それは昭和までさかのぼり、祖父の戦争体験へと繋がるのでした。
(A.K)
|
みうら じゅん/著 文藝春秋 大量のゴムヘビ、怪獣のスクラップ、英語が書かれた紙袋など、何に使うのか、そもそも必要なのかわからないけれど、自分にとっては大切なモノたち。「マイブーム」の言葉の生みの親みうらじゅん氏が、「死後、他人が捨ててしまうのは構わない。」と宣言しつつも「遺族は困るだろうけど、死ぬまで捨てられないもの」をマイ遺品と名付けて紹介します。 断捨離や終活など、物を減らしていく活動が推奨されている今、その流れにあがない、コツコツと自分にとっては大切ながらくたを倉庫を借りてまで収集していく様子には脱帽です。 (Y.M)
|
|
| 『絶望書店~夢をあきらめた9人が出会った物語』 | 『わたしのすきなもの』 | |
| 頭木 弘樹/編 河出書房新 人間、生きていれば夢を持つことができます。小さかった頃の夢は非現実的なものが多いのに、成長するとその夢は現実的なものに変わり、大人になっていくにつれ、夢の実現に向けて努力をすることになります。
自己啓発本は夢を持つことをすすめ、夢をかなえた成功談を語っています。でも、すべての人が夢を実現できるわけでもなく、夢を追っても実現できない人も多数存在します。
そんな人たちの絶望に寄り添うのがこの本。夢のあきらめ方にまつわる物語が集まりました。あの頃の夢の終着点を探してみませんか?
(A.U)
|
福岡 伸一/著 婦人之友社 生物学者として活躍中の著者が、自身の「すきなもの」について書いたコラムで、亡くなったお母さんが、生前熱心に読まれていたという雑誌「婦人之友」に連載されていたものが一冊になりました。
彼のすきなものは、「ハンミョウ」や「ドリトル先生」など、昆虫から物語の主人公、音楽、文房具など多岐に渡っています。そして、すきなもの一つ一つにまつわる思いが綴られています。
『「わたしのすきなもの」とは「私を育み、励まし、守ってくれたもの」』という著者のすきなものに対する愛と優しさが感じられます。
(R.K)
|