
| ◆目次 第1部 第二次計画の検証 □第1章 第二次計画における視点 □第2章 第二次計画における取組状況と成果
第2部 第三次 伊万里市子どもの読書活動推進計画 □第1章 計画の趣旨 □第2章 基本目標 □第3章 計画の目指すもの □第4章 子どもの読書活動推進のための方策
|
|||||||
|
伊万里市では平成16年に第一次となる「伊万里市子どもの読書活動推進計画」を策定し、平成22年にはその「第二次伊万里市子どもの読書活動推進計画」を策定して、子どもの読書活動の推進に取り組んできました。この期間中に市内の小中学校では朝の読書が100%実施されるとともに、学校への読み語り(読み聞かせ)ボランティアの活動も広がり、市内の読書に関するボランティアグループで構成した団体として「おはなしネットワーク」も組織されるようになりました。
また、地域では、公民館を中心に「家読実行委員会」が組織されるなど、子どもの読書に対する理解が少しずつ広まっています。それに伴い市民図書館での子どもの本の貸出冊数も増加しています。しかし、子どもの読書習慣の定着に向けては、家庭、地域、学校等が連携した社会全体での取組が大切であり、読書活動は短期間で結果の出るものではないため、さらに継続していくことが求められます。そこで、第二次計画に基づき、期間中の取組と成果や課題について次のように検証しました。
|
|
| 【 基本目標 】 『子どもが自主的に楽しく、読書に親しむ環境づくり』 子どもは、自主的に読書をするときには、本当に楽しみながら、いきいきとしています。この計画では、自然に子どもの手が本に伸びる環境の整備を目指します。
基本目標 : 子どもが自主的に楽しく、読書に親しむ環境づくり【 施策の体系 】 この計画は、基本目標を元に、次のような4つの章からなる総合的な体系で構築されています。 Ⅰ 家庭、地域、学校を通じた子どもの読書活動の推進 Ⅱ 読書活動推進のための施設、設備、図書資料等諸条件の整備・充実 Ⅲ 市民図書館、学校、幼稚園、保育園、社会教育施設、民間団体等の連携・協力 Ⅳ 子どもの読書活動を支える人材の育成及び社会的気運の醸成 |
第2章 第二次計画における取組状況と成果
1.家庭、地域、学校を通じた子どもの読書活動推進
(1)家庭における活動の推進
| ≪主な施策≫ ・ノーテレビデー・ノーゲームデーの実施 ・家読の推進 ・乳幼児期からの読み聞かせの推進 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・図書館や公民館にて「家読フェスティバ ル」をはじめ、講演会や講座の実施 ・ブックスタート実施 ・市民図書館から「家読おすめの本」のリ ストを毎月発行 |
(2)地域における活動の推進
①公民館や児童センター等における活動の推進
| ≪主な施策≫ ・「家読実行員会」の設置と家読の推進 ・学校や図書館等との連携 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・すべての公民館が館報に「家読おすすめ 本」など家読を取り上げた ・ボランティアによる図書室の土曜開館 (黒川公民館) ・「家読フェスティバル」が4館で行われ 他の館も別の館の名称で取組が行われて いる。 ・公民館まつりなどの行事に、絵本の読み 語りを取り入れた館がある |
③市民図書館における活動の推進
| ≪主な施策≫ ・本の案内、図書の展示 ・子どもの本の利用促進 ・乳幼児向け図書の充実 ・家読おすすめ本のリスト発行 ・ホームページの充実 ・自動車図書館巡回 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・おはなし012(乳幼児向け) 土曜おはなし会の実施 87回(平成26年度) ・テーマを決めた図書の展示(毎月) ・児童・生徒の図書館見学対応 81回(平成26年度) ・児童書の貸出冊数増加3.2%増 平成16年度貸出冊数 197.259冊 平成20年度貸出冊数 235.959冊 平成26年度貸出冊数 243.534冊 |
③民間団体等における活動の推進
| ≪主な施策≫ ・読み聞かせの研修会 ・幼稚園・保育園、学校、図書館等、 活動の場の拡充 ・おはなしネットワークでの情報交流 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・ボランティアグループによるおはなし ネットワークの会議の実施 ・小中学校における、ボランティアによる 読み語り実施率100% |
④障がいのある子どもの活動の支援
| ≪主な施策≫ ・録音図書・点字図書の充実 ・自動車図書館でのサービス |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・ボランティアによる布の絵本の作成 ・ひまわり園や伊万里特別支援学校への 自動車図書館巡回 |
(3)学校における活動の推進
①小学校・中学校・高等学校における活動の推進
| ≪主な施策≫ ・ノーテレビ・ノーゲームデー ・「読書カルテ」の活用 ・職員研修会の開催 ・図書館利用の指導 ・児童・生徒による読書活動 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・朝の読書実施率 100% ・職員研修会の開催 1回/年 ・リレーうちどくを12校が実施 ・学校図書館を利用するためのオリエンテ ーションを実施 |
②幼稚園や保育園における活動の推進
| ≪主な施策≫ ・絵本の読み聞かせの充実 ・保護者への家読の推進 ・教諭・保育士の意識の高揚 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・教員・保育士による絵本の読み語りの 実施 ・ボランティアによる読み語り等の実施 ・家読について、具体的な取り組みをして いる園もある |
2 読書活動推進のための施設、設備、図書資料等諸条件の整備・充実
(1)市民図書館の整備・充実
| ≪主な施策≫ ・市民図書館の整備と資料の充実 ・子ども向けホームページの充実 ・支援機能の強化 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・子ども向け資料の充実 88,048冊(平成27年3月末現在) ・幼稚園2園、保育園19園、学校17校への 自動車図書館の巡回と団体貸出 ・子ども向け図書館ホームページと家読ホ ームページの更新 |
(2)学校図書館の整備・充実
| ≪主な施策≫ ・施設、設備、図書資料の整備・充実 ・学校図書館が機能するための体制づくり ・ボランティアによる活動の充実 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・学校図書館標準図書の達成率 小学校 130% 中学校 106% ・学校図書館事務補助の全校配置 ・図書室の環境整備の促進 ・学校図書館担当職員の研修 |
(3)幼稚園や保育園における環境の整備・充実
| ≪主な施策≫ ・図書コーナーの設置 ・園児や保護者への貸出 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・廊下や空き教室や教室の隅など、場所を 工夫して図書コーナーを設置し、家庭へ 貸出をしている園もある ・月刊誌の定期購読を利用し、年齢に応じ たおはなしを子どもが読めるようにしている |
(4)公民館や児童センター等の社会教育施設における環境の整備・充実
| ≪主な施策≫ ・子どもが読書に親しむ機会の提供と環 境づくり |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・ロビーなどに寄贈本などを活用して図書 コーナーを設置する公民館が増えている |
(5)障がいのある子どもへの配慮
| ≪主な施策≫ ・市民図書館においての環境整備 |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・自動車図書館による、ひまわり園や伊万 里特別支援学校への巡回 |
3 市民図書館、学校、幼稚園、保育園、社会教育施設、民間団体等の連携・協力
| ≪主な施策≫ ・推進委員会を設置し、総合的に推進体制 を整備する |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・「伊万里市子どもの読書活動推進委員 会」の開催と事業の評価(年2回) ・地域内の連携・協力体制の充実 |
4 子どもの読書活動を支える人材の育成および社会的気運の醸成
(1)子どもの読書活動を支える人材の育成
| ≪主な施策≫ ・図書館職員等の資料選択に関する知識の 向上を図る ・司書、保育士等の読み聞かせ等の能力向 上を図る ・学校図書館についての研修を行い指導力 の向上を図る ・ボランティアの拡充を図る |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・図書館職員の児童サービス研究会の参加 ・長期休暇に幼稚園・保育園では研修会に 参加したところがあるが、時間の都合で 参加できない園もある ・学校図書館事務補助向け研修会の実施 ・読み語りボランティア講座の実施 |
(2)「子どもの読書の日」等への取組
| ≪主な施策≫ ・「子どもの読書の日」の普及 ・秋の読書週間においても、子どもの読書 活動へ取り組む |
⇒ | ≪主な活動と成果≫ ・市民図書館にて「子どもの読書の日」関 連事業の実施 ・学校図書館にて、年に1~2回図書館まつりを実施し、多くの児童が楽しみにしている |
第3章 アンケート結果から見た子どもの読書の現状
1 調査結果の比較
・読書活動に関するアンケートの結果
① 「読書が大好き、好き」と答えた割合
|
・「読書が大好き、好き」という児童が小学2年(79.4から82.6%)、小学5年(62.0から66.7%)と
中学2年(58.8から65.6%)と増えました。
② 「学校と家での読書を合わせてほぼ毎日読書をしている」と答えた割合
|
・「ほぼ毎日読書をしている」という児童もアンケートを実施したすべての学年において増加しています。
③「本を読まない(学校と家での読書を合わせて)」と答えた割合
|
④「家庭で、毎日子どもに読み聞かせをしている」と答えた割合
|
・「家庭で、毎日子どもに読み聞かせをしている」という保護者が、保育園(10.1%から5.4%)
幼稚園(19.0から9.3%)と減少しています。
⑤「一ヶ月で全く本を借りていない」と答えた割合
|
⑥「一週間のうち一度も学校図書館に行っていない」と答えた割合
|
・⑤と⑥の調査結果では、どちらの質問も小学2年と小学5年の割合は減少しています。
中学2年の割合は減少しましたが、年齢が上がるにつれ本を読まなくなったり図書館を利用
しなくなる割合が高くなっています。
第4章 第二次計画における課題
①読書時間と読書離れ
| アンケート調査では「学校と家庭でどれくらい本を読んでいますか」という質問に「ほぼ毎日読書をしている」が、小学5年生は5.1%、中学2年生が6.5%と大きく伸びています。また、「読書が好き」と答えた割合も3~4%伸びており、特に中学生が6.8%と大きく伸びています。一方、「本を読まない」という回答も中学生を除き微増しています。これはまだ少ないものの二極化状況がみられ、家庭を対象とした出前講座等により読書の楽しさを幼少期から伝えるなどして底辺の拡大を図る啓発活動等が必要です。 |
②読書環境の整備と資料の充実
| 家読運動の展開により幼稚園や保育園の玄関等に図書コーナーが設置され、一時的に「住民生活に光をそそぐ交付金」等の活用により学校の資料が整備されましたが、全体的に見ればまだ十分とは言えない状況です。これを補うため地域住民から図書の寄贈が行われています。さらに、学校のICT化が進められているなか、学校図書館のICT化はまだ着手されていません。 |
③司書の研修の充実
| 図書館サービスは、司書の経験の蓄積が大きな要素になります。このためには職員研修が必要ですが、学校図書館では臨時職員のため雇用期間が限定され、持続的な経験の蓄積ができない状況があります。今後、学校での調べ学習の展開や自ら学ぶ力を育てるためには、その対応が必要です。 |
④ボランティアの研修
| 図書館や全小中学校での朝読み等にボランティアが活発に活動しています。このボランティアの連携と共にレベルアップ等の研修が必要です。また、新規に始める人材の発掘もこれからの課題となります。 |
⑤「家読」の推進
| 図書館の他に4つの公民館で家読フェスティバルが開かれ、公民館まつりでも子どもの読書活動の取組が紹介されるようになりました。その中でボランティアグループは中心的役割を担っており、さらに広げていくためには、その組織化や育成が求められています。学校現場では、12の小学校でリレーうちどくが実施されていますが、読書活動が広がっていない学校との格差が懸念されています。 |
| 情報化やグローバル化社会の進展にあって、インターネットやゲーム、携帯電話などの情報メディアの普及や生活環境の変化により、子どもの「読書離れ」は、加速化してきました。そこで「子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きるための力を身に付けていく上で欠かせないものであり、社会全体でその推進を図っていくことは、極めて重要である。」として、平成13年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律(第154号)」が施行されました。 この法律に基づき、国の「第一次子どもの読書推進に関する基本的な計画」が平成14年に、第二次計画が平成20年、さらに第三次計画が25年5月に制定されました。その間、平成17年には、「文字・活字文化推進法」が成立し、平成19年の「学校教育法」の改正では、普通教育の目標のひとつに「読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し使用する基礎的な能力を養うこと」が新たに規定されました。さらに平成26年には、学校図書館法の一部改正が行われ、学校司書が初めて法律で位置づけられることとなりました。 佐賀県では、平成16年7月に「佐賀県子どもの読書推進計画」を策定し、家庭、地域、学校での子どもの読書活動に必要な取組を展開してきました。伊万里市においては、平成16年の第一次計画を見直し、平成22年に「第二次伊万里市子どもの読書活動推進計画」を策定しました。その間、平成19年には、全国の市では始めて「家読」に取組み、これを中心にこどもの読書環境の充実に努めてきました。また、平成22年10月には、市民図書館15周年を記念し、「こども読書のまち・いまり」を宣言し、ブックスタートや自動車図書館での保育園や小学校への巡回、小・中学校での朝の読書などにより家庭・地域・学校での子どもの読書活動推進を図ってきました。 しかし、依然として年齢が上がるにつれて、読書離れが顕著になる傾向は改善されておらず、学校図書館との連携や整備充実などさらに取り組むべき課題があります。また、障害者差別禁止法が平成28年度から施行されるので、これをふまえ障害のある子どもへも柔軟に対応していく必要があります。このため、全計画における事業の課題を検証し、「第三次伊万里市子ども読書活動推進計画」を策定しました。この計画に基づき、伊万里市のすべての子どもが、本と出会い、本に親しみ、生きる力と自ら学ぶ力を育てる読書習慣を身に付けていけるよう、行政はもとより、家庭・地域・学校・図書館及び関係団体が、さらに協力し、連携を深め、読書活動の機会の提供と環境整備に取り組んでいきます。 |
| 【基本目標】 「楽しく・いきいき・すすんで読書!」 子どもが自ら進んで読書をするときは、本当に楽しみながら、生き生きとしています。そこで『こども読書のまち・いまり』宣言の実現を目指して、子どもが読書を楽しみ、本を読む環境の整備に努めると共に、家庭・学校・地域や図書館などが連携して、朝読みや家読を始めとした読書活動を進めます。 【基本方針】 1.子どもの読書を支える環境づくり子どもが進んで読書に親しむためには、 ①いつでも どこでも 身近に本のある環境 ②読みたい本に出会える 豊富な資料 ③子どもに本を手渡す 専門的知識のある人が不可欠です。これらの読書環境の整備に努めます。 2. 家庭・学校・地域や図書館などの協働による取組 子どもが読書に親しむ機会の充実のため、家庭、保育園、幼稚園、学校、公民館及び図書館がそれぞれの役割を果たし、協働を進めるように努めます。 3.子どもの読書活動の意義及び意識の啓発並びに家読の普及 子どもの主体的な読書活動を進めるためには、保護者や教師、保育士等、子どもに身近な大人が、読書への理解と関心を深めることが大切です。子どもを取り巻く地域社会全体で、子どもの心を育てる読書活動の意義や重要性について、普及・啓発を図り、家読の推進に努めます。 【計画の実施期間】 平成28年度から平成32年度までの5年間とします。 また、子どもの読書活動推進委員会において、実施状況の確認を行います。 |
| 【図書館】 | 【家庭・学校・地域】 | |
||
|
・YAコーナー
・おすすめの本リスト
・職場体験の受け入れ ・郷土資料の活用 ・読み語り ・こども映画会 ・オリエンテーション ・おすすめ本のリスト ・ぶっくん巡回 ・読み語り ・おはなし会 ・ぶっくん巡回 ・布タペストリー絵本 ・ブックスタート ・赤ちゃん絵本 ・おはなし012 ・授乳コーナー |
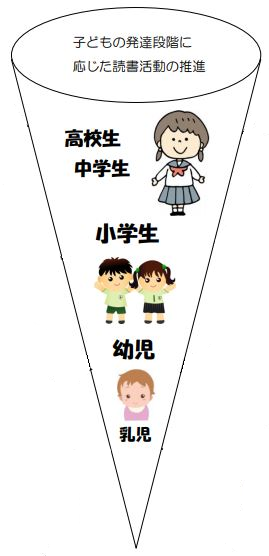 |
・学校での朝読書 ・地域での読書活動 ・家読のすすめ ・学校での朝読書 ・地域での読書活動 ・学校と地域の連携 ・リレーうちどく ・幼稚園・保育園での 読書活動の推進 ・読み語り ・家読のすすめ ・読み語り ・家庭での読書活動 |
第4章 子どもの読書活動推進のための方策
(1)家庭における子どもの読書活動の推進
| テレビやゲームとともにインターネットや携帯電話などの急速な普及は、大人だけでなく子どもたちの生活環境も大きく変化させました。子どもの生活時間の変化や物事に対する興味や関心の多様化は、読書習慣の形成を妨げる一つの原因であり、「読書離れ」や「活字離れ」を引き起こしています。また、保護者自身の読書への関心も低下しています。子どもにとって一番身近な読書環境は家庭です。家庭の中で大人が、子どもの読書活動の意義や重要性について理解し、率先して読書に親しみ、家族ぐるみで読書する環境をつくることが必要です。そのため、本市では平成19年から家読に取り組んでいます。平成27年のアンケートでは、5歳児の家庭で毎日読み語りをしている割合が、前回に比べ半減していることが判りました。そこで、今回の計画では、保護者に向けて家読の実施を積極的に働きかけていくことを目標に掲げます。 |
| ◆目標 ①子どもに関わるあらゆる機関における、あらゆる方法での読書の啓発 ②家庭での読書習慣の形成 ③家読の推進 ◆方策 ①家庭への理解の促進 3ヶ月健診のブックスタートで絵本とパンフレットを手渡しているが、引き続き年齢に応じ絵本の大切さを伝える資料や本のリストを配布します。図書館だよりや市の広報誌、各機関からの刊行物、園や学校からのお便りでも家読を呼びかけます。 ②保護者の学習機会への参加 家庭教育に関する講座や、保育園・幼稚園、学校などで開催される家読や読書の啓発事業に参加し理解を深めます。 ③家読の実施 家読やノーテレビ・ノーゲームデーを子どものいる家庭で実施します。 やり方の例としては、各家庭でルールを決めてもらう、又は園・学校・学級単位で取り組む「寝る前の読み語り」「毎日15分読書」に積極的に参加するなど、が挙げられます。 |
(2)地域における子どもの読書活動の推進
| 地域コミュニティの拠点である公民館では様々な社会教育活動を展開しています。 世代を越えて地域住民が集まる場所ですので、子どもだけでなく大人も関わりが持てるような取組を行うことで、子どもの読書活動を地域に広げていくことができます。そのためには本のある場所を整備し、地域で活動しているボランティアを中心として、読書の関連行事を開催するなど、地域への啓発活動が必要となってきます。 |
| ◆目標 ①公民館、留守家庭児童クラブ及び児童センターの読書環境の整備 ②地域の読書活動団体への支援 ③本に触れる機会の創出 ④家読の推進 ◆方策 ①公民館や留守家庭児童クラブ、児童センターに絵本・児童書を設置 地域の拠点となる公民館に図書室や図書コーナーを設け、子ども向けの絵本や児童書を置くことで、本との出会いの場を広げます。また、子どもたちが多く集まる留守家庭児童クラブや児童センターに本を置く場所を作り、図書館から団体貸出などで支援を行います。 ②読み語りボランティアの支援 子どもへの読み語りなど読書活動を行うボランティア団体へ、会員募集のお知らせや練習場所の提供などの支援を行います。希望があれば、公民館や留守家庭児童クラブに出向いてもらい、おはなし会を開催して子どもたちが楽しめる場を設定します。 ③公民館報への掲載 家読おすすめの本を掲載することで、新刊図書の情報提供や、読書活動の啓発を行います。 ④家読フェスティバルの開催 地域が主体となり、物語や読み語りに関するイベントを開催することで、地域住民への家読の理解を深め、読書活動推進の機運を高めます。 |
(3)幼稚園・保育園における子どもの読書活動の推進
| 子どもの生きる力を育てるには読書が不可欠です。読書は早い時期からの習慣づけが大切で、幼稚園や保育園の果たす役割は大きいものです。幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、乳幼児が絵本や物語などに親しむ活動を積極的に行います。あわせて、保護者に対し読み語りの大切さや意義を周知します。 |
| ◆目標 ①幼稚園・保育園における読書環境の整備 ②教諭・保育士による読書活動の充実 ③家読の推進 ◆方策 ①図書コーナーの整備 子どもが絵本に親しむ機会を確保する観点から、安心して図書に触れることができるようなスペースの確保に努めるとともに、図書の整備を図っていく必要があります。0歳児から5歳児までの発達段階に応じた資料を揃え、園内で活用するだけでなく、家読につなげるために、貸し出しも促進します。物語絵本をはじめ、生き物、食べ物、生活習慣など様々な子どもの興味に応える資料を幅広く揃えます。資料が不足する場合は市民図書館の団体貸出を利用して補います。 ②職員研修の充実 子どもが本への関心を深め、読書に親しむようになるためには、子どもに携わる人たちの児童図書に関する理解が必要です。そのため、教諭・保育士一人一人が読書の重要性を学び、児童図書に関する知識と、おはなしの手法などを深めるために学習会を園内で行います。また、研修の機会があれば積極的に参加し、学んだことを共有します。 ③教諭・保育士による日常的な読み語り 子どもにとって、多くの時間を過ごす園での読書活動は重要ですので、教諭・保育士や友だちとの日常の生活の中で絵本を楽しみ、たくさんの本に触れる機会を作ります。さらに、保護者や地域のボランティアが行う読み語りの活動を積極的に受け入れます。 ④家読とノーテレビ・ノーゲームデーの実施 子どもの成長に読書が大切なことを保護者に啓発するとともに、具体的な取組を家庭へ提案します。リレーうちどくなど、先進地区の事例を参考に、保護者会などと相談しながら無理のない形で家読とノーテレビ・ノーゲームデーに取り組みます。 |
(4)学校における子どもの読書活動の推進
| 子どもを取り巻く生活環境は日々変化しています。学校図書館は、子どもが自ら本に出会い、読書の楽しみを見つけることができる場です。各年齢で出会うべき読書は、子どもの夢を育み、生きる力の源になるものです。読書の習慣形成、知的活動の推進のため、様々な興味や関心に応える魅力的な学校図書館として資料を整備・充実させていくことが必要です。 学校図書館は、児童・生徒が自ら学ぶ「学習センター」、「情報センター」としての機能と、豊かな感性や情操を育む「読書センター」としての機能があります。そして、それぞれの機能を果たすことが、「資料、施設・設備、人」に期待されています。学校図書館は、司書教諭や学校司書だけで運営するのではなく、そこに携わる人たちすべてが利用し、育てていく場として考えます。 |
| ◆目標 ①学校図書館の機能の明確化 ②学校図書館の整備・充実 ③学校司書・司書教諭の配置 ④職員の読書推進・研修 ⑤本との出会いへつながる子どもの読書活動の推進 ◆方策 ①読書センター、学習センター、情報センター機能の充実学校図書館の多様な機能を充実するために、図書館のネットワーク(情報、物流の確立)の構築を目指します。 ②「図書館を使った調べる学習コンクール」への参加子どもが自ら学ぶ力を成果に結びつけるために、平成28年度より伊万里市教育委員会が主催する「伊万里市民図書館・学校図書館を使った調べる学習コンクール」へ参加します。 ③児童・生徒が行きたくなる心のオアシスとしての図書館 児童・生徒が進んで読書を楽しむために、自然に足を運びたくなるような明るく落ち着いた学校図書館環境の構築を目指します。 ④学校図書館の資料の充実 豊富で多様な図書資料の整備のために、「学校図書館図書標準」をふまえ、資料の利用状況や資料状態を学習内容等に照らし合わせて見直し、使えなくなった資料を除籍し、買い替えを含めた蔵書の更新を行うことで、内容を伴った蔵書構築を目指します。合わせてリサイクル本や寄贈本の活用を推進します。 ⑤学校司書・司書教諭の配置 学校図書館法の一部を改正する法律第六条により、「学校司書」の名称や職務等が明記されました。学校図書館をより充実し、有効的な機能を果たすためには、学校司書の役割が重要で、そのため学校司書の職務内容を明確化し、専門職としての人材育成を計画していく必要があるので、各学校への配置が進むように働きかけを行います。 ⑥職員の研修 すべての教員を対象とした読書活動に関わる研修会の実施を計画し、研修受講を奨励します。また、司書教諭をはじめ、学校図書館事務補助や図書館担当職員の研修会を実施し、児童・生徒の読書活動に関わる職員のスキルアップを目指します。さらに、学校図書館事務補助研修会では、読書活動ボランティアとの連携など研修内容の充実を図ります。 ⑦読書指導の拡充 授業において、積極的に学校図書館や市民図書館を活用し、児童・生徒の読書指導や図書館利用指導の充実に努めます。また、読書感想文や読書感想画コンクールなどへの取組を通して、読書活動が表現活動につながるようにします。 ⑧全教職員による読書活動の推進 教職員自らが読書に親しみ、読書指導や全校一斉読書活動並びに読み語りなどの読書活動の推進を行います。また、図書委員をはじめ、児童・生徒による本の紹介などの活動を奨励し、児童・生徒の自主的な活動(図書委員会や児童会・生徒会活動など)を活性化します。 図書館便りの発行やおすすめ本のコーナー設置、新刊情報や授業内容に合わせたブックリストの作成、ブックトークでの児童・生徒へおすすめの本の紹介など、読書活動に関する啓発活動の充実を目指します。 ⑨本との出会いへつながる子どもの読書活動の推進 ノーテレビデー・ノーゲームデーの奨励とともに、保護者に対して読書を中心とした子どもとのコミュニケーションの重要性をPRします。また、「リレーうちどく」の活用により、学校と家庭とが連携した家読を推進します。さらに、ボランティアの協力を得て、読み語りの活動を支援するなど、地域人材の活用を推進し、学校や市民図書館、読書活動ボランティアとのネットワーク構築を目指します。 |
(5)公共図書館における子どもの読書活動の推進
| 公共図書館は子どもが誰でも利用でき、本との出会いや読書の楽しさを体験できる場所です。市民図書館では「ブックスタート事業」を始め、各種おはなし会、自動車図書館巡回など、様々なサービスを展開して、子どもの成長に合わせて切れ目のないサービスこれまで行ってきました。今後は、これらのサービスを市内の隅々まで広げて定着させることと、充実を目指していくことが重要な課題となります。また児童サービス・青少年サービスを提供し続けるためには、担当職員が専門的知識・技能を修得し、ボランティアとの連携を図っていくことが不可欠です。さらに、市で取り組んでいる家読についても、理解を深める啓発活動や研修の場を設けるなど、家読活動の普及・推進に取り組んでいきます。 |
| ◆目標 ①市民図書館の整備・充実 ②子ども向けサービスの充実・強化 ③公民館等への支援 ④研修機会の確保 ⑤家読の推進 ◆方策 ①市民図書館の蔵書の充実 ブックスタートや乳幼児向けおはなし会の実施に伴い、乳幼児向け資料の充実を図ると共に、自動車図書館での巡回や団体貸出にもおすすめの図書を貸出できるよう、世代別に絵本や児童書を充実させます。 ②市民図書館の利用促進 小学生以下の子どもは大人の同伴が必要なことから、大人に対しても積極的なPRを行い、親子で来館して図書館を利用するような働きかけを行います。 ③公民館等への支援 図書室や図書コーナーが無い施設に対して、身近に本のある環境を整備するため、団体貸出などの支援を行い、読書環境を整備します。 ④家読推進講演会の開催 家庭・学校・地域が連携して取り組む家読活動の理解を深めるため、研修の場を設けることで、家読の取組を発展させ、読書活動の啓発を行います。 ⑤家読ホームページの充実 地域や時間にとらわれず、必要な情報を掲示したり、イベントの紹介を行ったりすることで、家読活動の情報提供を行います。 ⑥「図書館を使った調べる学習コンクール」地域コンクールの開催 家読で培った読書の力を、図書館の資料を活用して子どもが自ら学ぶ力へと繋げるために、平成28年度から「伊万里市民図書館・学校図書館を使った調べる学習コンクール」を開催して、市内から広く作品を募集します。募集した作品は審査を行い、優秀なものについては表彰すると共に、全国規模の「図書館を使った調べる学習コンクール」への出品を推薦します。 |
(6)関係機関の連携
| 本計画の推進については、市全体で一致協力して取り組む必要があります。伊万里市に育つ全ての子どもたちの健やかな成長のために、関係する各機関・団体が連携し、子どもと本をつなぐ全ての人たちが読書活動の推進に取り組んでいくことが重要です。 |
| ◆目標 ①子どもの読書活動の推進体制の整備 ②市民図書館を中心とした、子どもにかかわる関係機関・団体の連携と協働 ③年代に切れ目のない子ども向けサービスの展開 ◆方策 ①伊万里市子どもの読書活動推進委員会の定期的な開催と活性化 本計画の推進にあたり、関係団体の連携・協力を図るため、関係者で構成される推進委員会を設置し、相互に情報交換や活発な議論及び事業の評価を行うための総合的な推進体制を整備します。 ②市民図書館と関係機関・団体の連携 これまでも様々な場面で市民図書館と関係機関・団体は連携・協働して、子どもの読書活動を推進してきましたが、さらに連携を強化しながら状況に合わせてつながりを広げていくように進めていきます。 ③地域内での連携と協力 公民館単位で13の地区に分かれているので、それぞれの特徴を生かして地区内の幼稚園・保育園、学校、社会教育施設、民間団体等が連携して、特色ある取り組みを行います。 ④ブックスタート事業の推進 赤ちゃんから本に接する機会を作り、子どもの成長に合わせて読書活動が展開されるように進めるには、開始地点であるブックスタートが重要となります。市民図書館とボランティアが連携し、継続して事業を行います。 |
(7)行政の役割
| 子どもの読書活動を推進するには関係する各機関・団体の働きが重要ですが、それだけでは補えない部分があります。市の施策としても、子どもの読書活動の推進に取り組み、さらなる読書活動の環境整備が必要とされています。 |
| ◆目標 ①子どもの読書に関わる人材の育成 ②普及啓発活動の推進 ③優れた取り組みの奨励 ④読書環境の整備 ◆方策 ①子どもの読書活動を支える人材の育成 子どもと本をつなぐ役割の司書や学校等の職員の能力向上と合わせ、読み語りやブックトーク等を実演・実践できるボランティアを育成するための研修会を開催します。 ②「子ども読書の日」及び「子ども読書週間」並びに「家読の日」への取り組み 子ども読書の日(4月23日)と合わせて、子ども読書週間(4月23日~5月12日)についても、市民図書館を中心として啓発活動を進め、記念行事や読書に関連する行事を開催します。さらに、毎月第3日曜日を「家読の日」と定めて、教育委員会で啓発活動を行うとともに、どの地域でも家読に取り組みやすい雰囲気を作りだすようにします。 ③子どもの読書に関する各種情報の収集・提供 市民図書館で本や読書に関係する情報を集めて、関係機関・団体に効果的に活用できるように提供します。また、幼稚園・保育園、学校、社会教育施設、民間団体等でも子どもや周りの大人に積極的に情報を提供していきます。 ④優れた取組の奨励と優良図書の普及 市内で活発に活動している各種機関や団体・個人について、子どもの読書活動優秀実践校、図書館、団体(者)の文部科学大臣表彰への推薦を行うとともに、市でも表彰を行います。また、社会保障審議会や全国学校図書館協議会等で推薦された優良図書の周知・普及を図ります。 ⑤財政上の措置 市における子どもの読書活動の環境を充実させるために、必要な財政上の措置を講ずるように努力します。 |